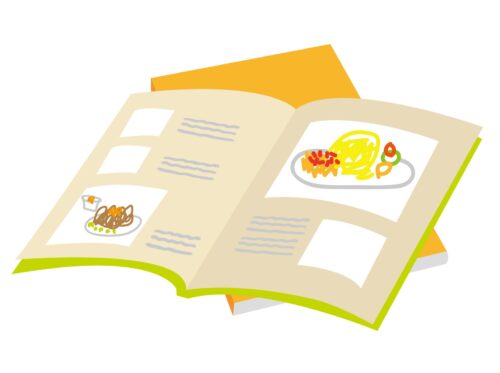褐色脂肪細胞を活性化!溜め込んだ脂肪を手放そう
2025年2月号2025年がスタートし、早くも2月が始まりました。年末年始の食べ過ぎや運動不足によって脂肪を溜め込んでしまっていませんか?今回は、体に溜め込んだ脂肪を手放すために利用したい『褐色脂肪細胞』の活性化について解説します。

脂肪細胞とは
脂肪細胞には、大きく分けて白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2種類があります。
『脂肪分を貯蔵し、エネルギーを蓄える』白色脂肪細胞
体内の脂肪のほとんどを占める脂肪細胞で、下腹部、お尻、太もも、背中、腕の上部、内臓周りといった全身の様々な部分に存在します。
中性脂肪や糖などを取り込み、脂肪として蓄えることで、内臓の保護や断熱作用など大切な働きを担っています。しかし、太る細胞とも呼ばれており、白色脂肪細胞が増加しすぎたり、1つ1つの細胞が大きくなりすぎてしまうと生活習慣病の発症リスクになるため注意が必要です。
『寒冷刺激により活性化し、肥満予防に役立つ』褐色脂肪細胞
名前の通り茶色の脂肪細胞で、主に首や肩甲骨、脇の下、心臓や腎臓の周りなど限られた場所にのみ存在します。エネルギーを生成するミトコンドリアが多く、体内に蓄えた余分な白色脂肪細胞を燃焼させて、「熱」を作り出す働きがあり、脂肪燃焼を促す働きから肥満予防に役立つのではないかと期待される細胞でもあります。
特に、寒い環境下では、体温が下がり過ぎてしまわないように熱を産生しています。このように寒い刺激によって活性化するため1年の中で最も寒いとされる2月は褐色脂肪細胞を活性化しやすいとされています。
<褐色脂肪細胞は減少していく?!>
体温調節機能が未熟な新生児期に最も多く、成人になるにつれて褐色脂肪細胞の数は減少します。これは、成長とともに体を守るために働いていた褐色脂肪細胞に代わって、骨格筋が発達し体温調節を担うようになるためと考えられています。
また、褐色脂肪細胞の働きには大きな個人差があり、活発に働く人は同じ量を食べても太りにくい傾向にあります。また、細胞の量は遺伝によるものが多く、基本的に成人すると増やすことはできないため、いかに活性化するかがポイントです。
今日からはじめる褐色脂肪細胞を活性化のポイント!
褐色脂肪細胞の活性化のポイントは、「交感神経を刺激すること」と「冷たい刺激」の大きく2つです。
寒さの刺激を活用する/寒い環境下に身を置く
体が寒さを感じると、身を守るために情報が脳へと伝わり、交感神経を活性化します。その結果、褐色脂肪細胞が活性化し、体温が下がりすぎないように熱を産生します。
これは、寒冷刺激によって神経伝達物質のノルアドレナリンが分泌され、褐色脂肪細胞にある受容体を活性化します。そして、熱産生を担う分子の発現量を増加するためと考えられています。しかしながら、体の冷えは不調をもたらすだけでなく、褐色脂肪細胞の働きも鈍くしてしまうので慢性的な冷えには注意をしましょう。
肩、肩甲骨周りを動かす
肩甲骨周りには褐色脂肪細胞が集まっているため、定期的に肩を回したり、すくめたり、肩甲骨周りを積極的に動かしてみましょう。肩回りを動かすことにより周囲の血流も良くなり、刺激によって交感神経も活発になります。また、姿勢が悪くなると、姿勢を支える筋肉が使われず、筋肉が凝り固まり、血行が悪くなって冷えやすくなります。巻き肩などに注意し、体幹を意識し、姿勢を正すだけでも活性化につながります。
食べものをよく噛む
安静時に、「噛む」という咀嚼刺激が脳に伝わると、交感神経が刺激されます。そして、褐色脂肪細胞が活性化し、体脂肪がエネルギーに変わるのを助けてくれるのです。さらに、食事をゆっくりと、よく噛んで食べることによって、満腹中枢も働き、食べ過ぎの予防にもつながります。一口ごとに箸を置き、よく噛むことを意識してきましょう。
脂肪を減らそうと極端な食事制限は、上手に体の熱が作れず、体の冷えにつながるだけでなく、食事の楽しみが減り、かえってストレスになりがちです。食事は適量をよく噛み、肩甲骨周りを動かして、この時期に活性化しやすい褐色脂肪細胞を味方につけてみてはいかがでしょうか。
生活・健康のリズムに
興味がある方は
文部科学省後援 健康管理能力検定3級・2級
健康管理のスペシャリストを
目指す方は
健康管理士・文部科学省後援 健康管理能力検定1級
category
- 季節の健康(27)
- 今話題の健康ワード!(11)
- 日本の郷土料理(48)
- ハーブ・アロマと健康(13)
- おいしさの秘密(12)
- ストレス解消法(12)
- 世界の人々の暮らし(12)
- 体に必要な「ミネラル」ってなんだろう??(12)
- 行事食(12)
- 四季を感じる食と食養生(26)
- 香りのパワーでこころとからだをリフレッシュ(8)
- こころがもたらす体のサイン(8)
- 今日からはじめる健康づくり(17)
- 気になる症状におすすめの食材(18)
- スリム&きれいに(8)
- 気になるからだの危険信号(45)
- 自然治癒力を高める(10)
- 健康診断・生活習慣病(9)
- 感染症(13)
- 新しい生活様式(10)
- 筋肉をもっと知ろう(11)
- 何気ない不調の解消法(11)
- 病気について知る(5)